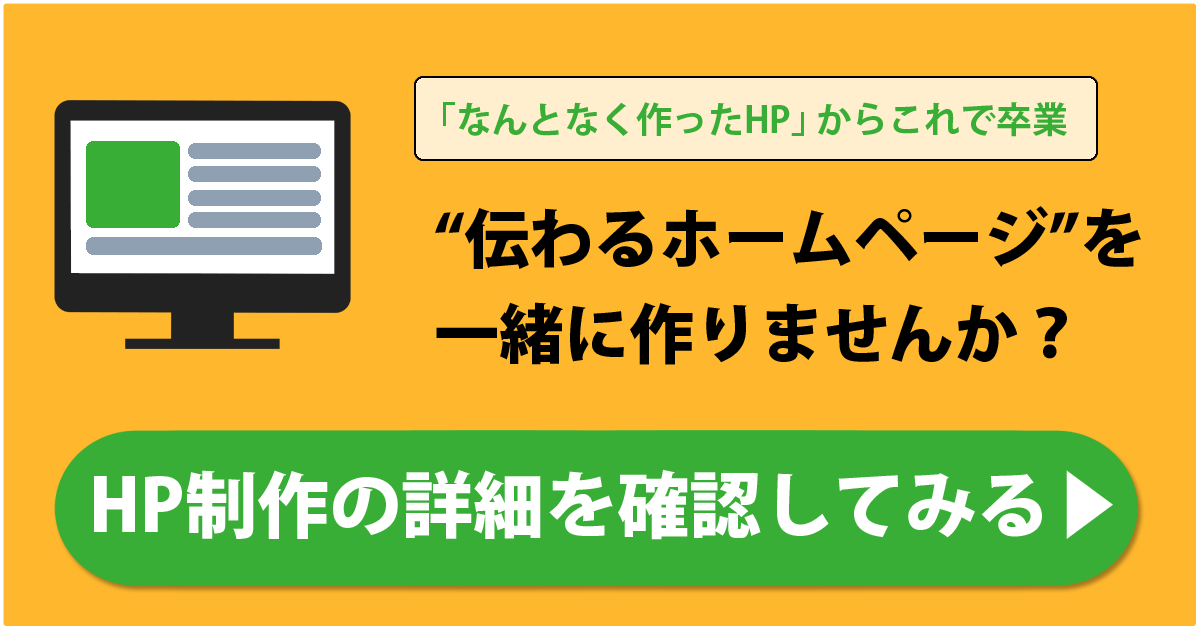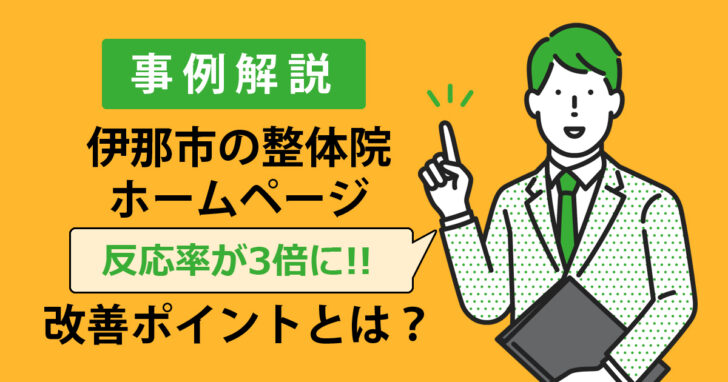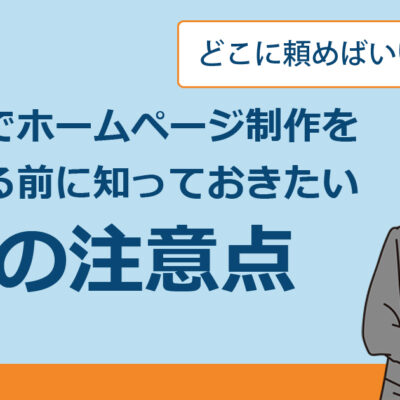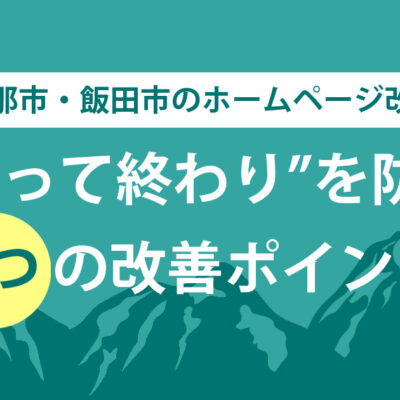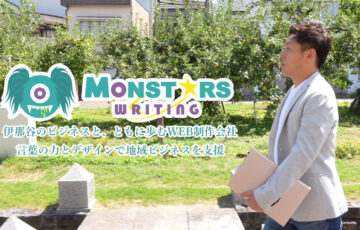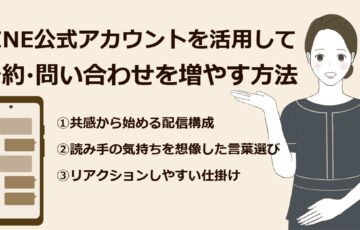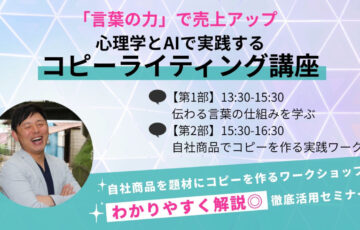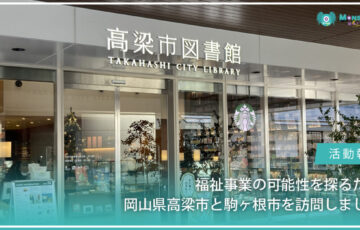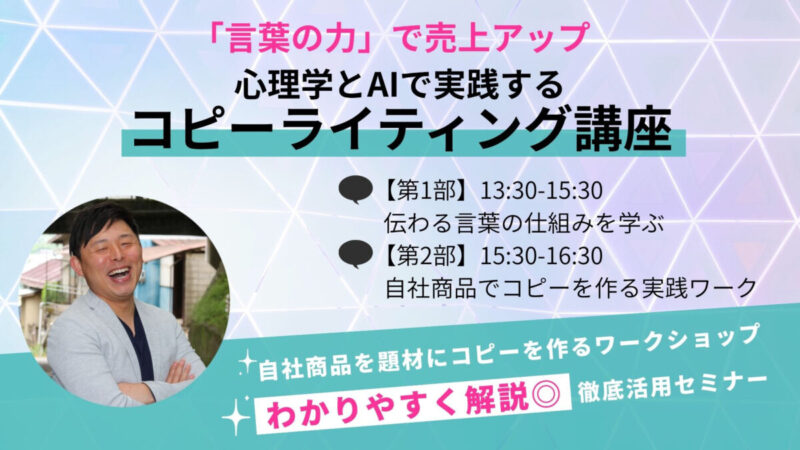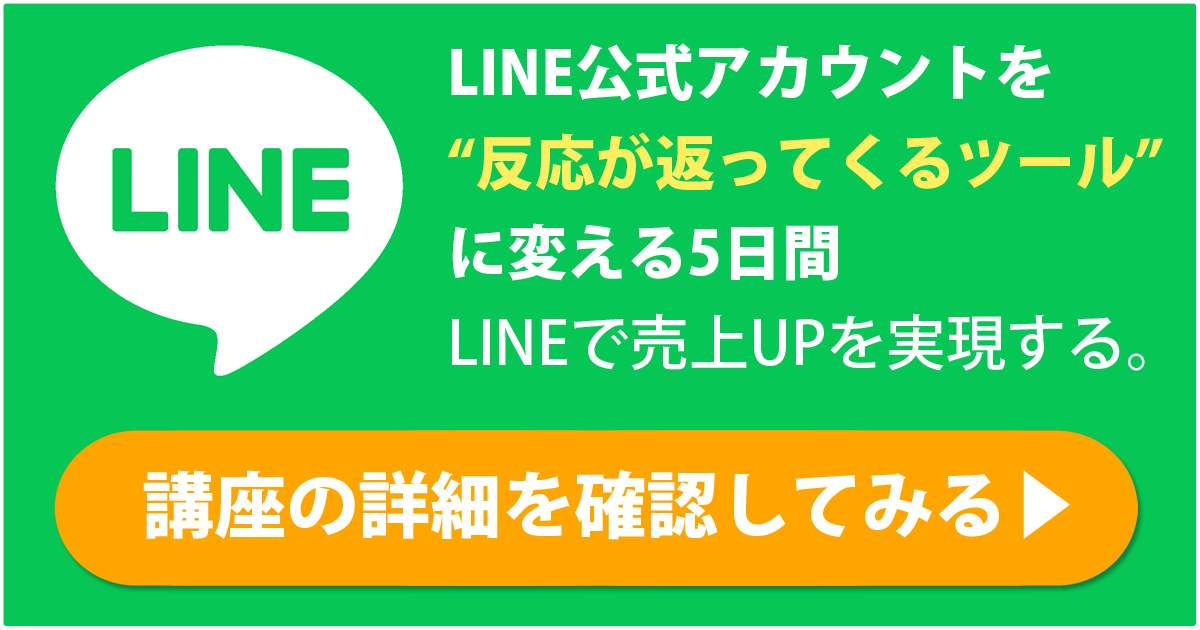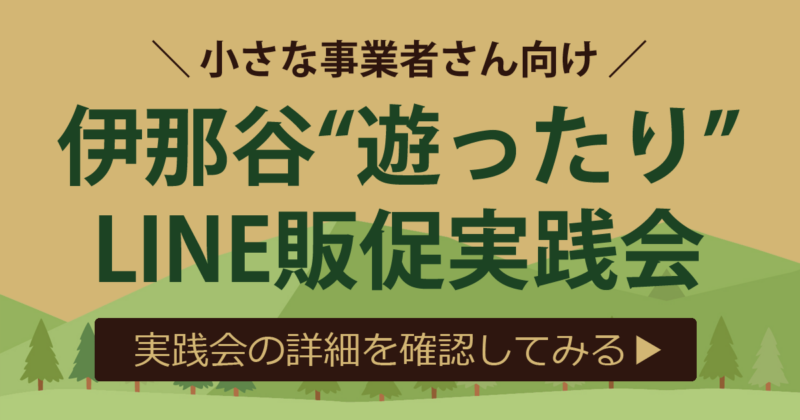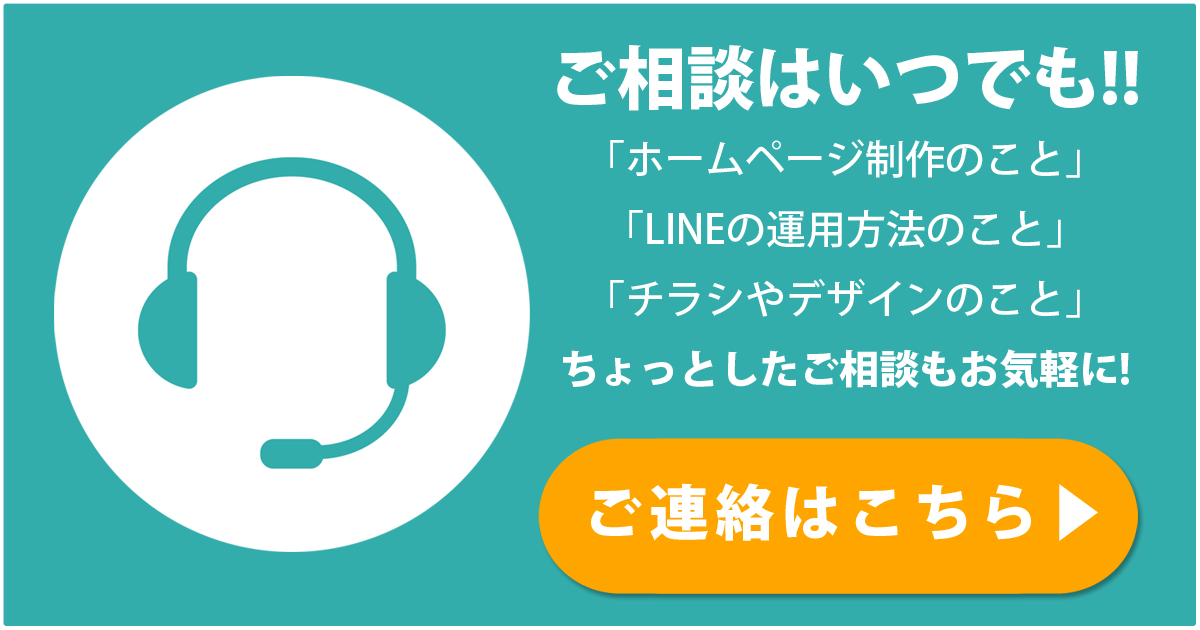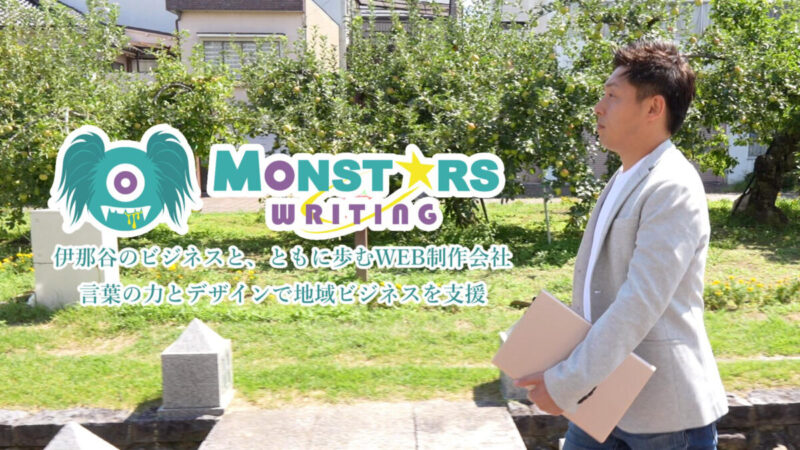今回の事例は「ホームページはあるけど、武器になっていない」というお話を解説していきます。飯田市・伊那市をはじめ伊那谷で事業を営んでいる小さな会社や小さなお店の事業者の方には必見です。「自分のこと」だと思って、自社のホームページの改善にお役立てください。
「ホームページを作ったのに、なぜか反応がない…」
そんな声を、地域の整体院や個人店舗からよく耳にします。

伊那市で整体院を営むAさんも、まさにそんな悩みを抱えていた一人でした。
開業と同時にホームページを立ち上げ、Googleマップにも登録。
でも、お問い合わせフォームもLINEも、数週間ずっと“沈黙”が続いていたそうです。
「なにかがおかしいのは分かるんですが、自分ではもう限界で…」
と相談を受けたのが、この改善のはじまりでした。
「改善」はとても大切です。私自身もそうですが、「一発でうまくいけばラッキー」で「基本的には改善ありき」で考えています。世の中にはPDCAサイクルという言葉もあるくらいですから、改善していくことにより成果も出てくることの方が自然です。
今回の記事では、実際に行ったホームページ改善の流れを、
「ビフォーアフター形式」でわかりやすくご紹介していきます。
- どんな表現をどう変えたのか?
- どこに行動導線を加えたのか?
- なぜそれで反応が3倍になったのか?
この記事を読めば、
「やみくもにリニューアルする前に、こういう視点が大事なんだ」
ということが、きっと見えてくるはずです。
「今あるホームページがなんとなく機能していない…」
そんな方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の内容
改善前の状態:一見問題なさそう。でも、反応ゼロ。

Aさんの整体院ホームページを最初に見たとき、正直「それほど悪くない」という印象でした。
(これは地域ビジネスの現場でもよくある話で、デザインが整っていると“それだけで良いサイト”に見えてしまうものです。ですが、「デザインがいい=結果が出る」とは限りません)
- 清潔感のあるデザイン
- メニューやアクセス情報もきちんと掲載
- Googleマップも表示されている
- スマホにも対応していて、見やすさに配慮されている
「これで反応がないって、おかしくない?」と感じる方もいるかもしれません。
でも実際には、お問い合わせも予約もまったく入っていなかったのです。
詳しく見ていくと…
- 誰に向けたページなのかが曖昧
→ 「どなたでも歓迎」と書かれているが、読み手の心には届いていない - サービスの強みが抽象的
→ 「当院は丁寧な施術を心がけています」だけでは、違いが伝わらない - 文章が長く、ブロックのように並んでいて読みづらい
→ スマホで読むには負担が大きく、途中で離脱されていた - 「お問い合わせはこちら」が下の方に小さくあるだけ
→ 行動を起こす導線が弱く、「どうすればいいか」が伝わらない
つまり、“伝えるための設計”がされていなかったんです。
見た目は整っているのに、相手に届かない…これは地域のビジネスでも非常によくあるケースです。
このブログでもたびたびお伝えしていますが、
「誰に伝えるのか」が曖昧なままでは、ホームページも広告も思うような結果は出ません。
たまたま刺さればラッキー。でもそれは再現性がなく、ビジネスとしては危うい。
私自身は偶然ではなく“必然で結果が出る仕組み”をつくることを大切にしています。
そのために必要なのが、「誰に・何を・どう伝えるか」をきちんと整理すること。
そして、それでもうまくいかないときは“改善”する。
これが成果につながる唯一の近道だと考えています。
改善ポイント①:誰に向けて、どんな言葉で伝えるかを明確にした
改善の第一歩は、「誰に向けて、どんな悩みに応える整体院なのか?」を明確にすることでした。
もとのホームページでは、「地域密着」「幅広い症状に対応」「丁寧な施術」など、
どの整体院でもよく見かけるような、いわゆる“当たり障りのない表現”が並んでいました。
もちろん間違いではありません。でも、それでは読み手の心には刺さらないのです。
刺さらないというより、地域に同じような整体院(競合)が多ければ多いほど、選ばれる理由にはならないのです。他でも似たような表現が多ければ、「どこでもいいよね」ということになります。そうなるとあとは家から近いなど、すぐにはどうにもできそうな他の要因で決まってしまうことも多いです。このままでは素敵な整体院でももったいないですよね。
実際に行ったこと
まずは、院長Aさんに「どんなお客さんが多いですか?」「理想のお客さん像ってありますか?」とヒアリング。
すると、こんな特徴が浮かび上がってきました。
- 40代〜50代の女性が多い
- 肩こり・首こり・頭痛の悩みが多い
- 「薬に頼らず、体を根本から整えたい」というニーズがある

そこで、ホームページの冒頭にこういったコピーを追加しました。
「最近、肩こりがひどくて…」というあなたへ。
しっかり“ほぐす”だけでなく、“整える”ことを大切にしています。
こうすることで、「あ、自分のことかも」と思って読み進めてもらいやすくなったんです。もしもう少し具体的にするのであれば、年齢層もコピーに追加してもいいかもしれません。若い層が反応しなくなる代わりに、同じ40代〜50代の新規層にヒットする可能性が出てきます。
たとえば若い層より明らかにこの世代の方の方がお金を使うということであれば、若い層をあきらめて、この世代の方に向けたホームページにした方が、トータルの売上が増えることになります。
この事例ではそこまでせずに、「上記のコピーで」ということになりました。
結果どうなったか?
- 滞在時間が伸びた(すぐ離脱する人が減った)
- LINE登録からの相談が増えた(“気軽に聞いていい”と感じた)
- 「まさに私のことだと思った」と言われることが増えた
ターゲットをぼかして“誰でもOK”にすると、実は“誰にも届かなくなる”。
この改善でそれを強く実感しました。
改善ポイント②:見せ方と流れを整えて、伝わりやすくした
ホームページの改善で意外と見落とされがちなのが、「伝える順番」と「見せ方の構成」です。
Aさんの整体院のもともとのページは、
サービス内容・こだわり・プロフィール・アクセス情報などが“とりあえず並んでいる”状態でした。
必要な情報は揃っているけれど、どこに何が書いてあるのかがパッと分からず、読んでいるうちに離脱してしまう人が多かったんです。
実際に行ったこと
今回の改善では、以下の3つを意識して順序と構成を再設計しました。
- 冒頭に「共感」から入る
→ 読者の悩みに寄り添った一言で、「これは自分の話だ」と思ってもらう。 - 次に「安心感」や「信頼できる理由」
→ 開業歴・実績・資格・地域での評判など、“選ばれる理由”を自然に伝える。 - 最後に「行動導線」へとつなげる
→ LINE登録や予約ページなど、迷わせない形で誘導する。

これだけでも、ホームページ全体が「ストーリーとして読める構造」になり、
ページを閉じる前に自然と行動してもらえる流れができたんです。
結果どうなったか?
- ページのスクロール率が上がり、最後まで読まれることが増えた
- LINEや予約ページへのクリック率が改善
- 「読んでるうちに行ってみたくなった」という声が増加
情報が“あるかないか”ではなく、
「どの順番でどう見せるか」で、同じ内容でも伝わり方がまるで変わる──
この改善で、その重要性を改めて実感しました。
改善ポイント③:「読んだあとどうするか?」を明確に設計した
整体院のようなサービス業では、
「なんとなく気になる」で終わってしまうか、「じゃあ予約してみようかな」と思ってもらえるか?
この差は、“行動を促す導線”を用意しているかどうかで大きく変わってきます。
Aさんのホームページでは、以前は「お問い合わせはこちら」のリンクが1カ所だけ、しかも目立たない場所にあるだけでした。
それでは、せっかくページを読んでも、“次に何をすればいいのか”がわからず離脱してしまう人が多かったんです。
実際に行ったこと
以下のような導線の工夫を加えました。
- ページの途中と最後にCTAボタンを設置
→ スクロール中でもアクションしやすいように「LINEから相談できます」ボタンを配置 - 「このメニューが気になる方は“気になる”と返信ください」など軽い一言を追加
→ 返信ハードルを下げることで、LINEの反応率がアップ - “今すぐ行動する理由”を添える
→ 「今週は予約が取りやすくなっています」「◯日までのご予約でプレゼントあり」など、軽い限定性を加える
これにより、ただ情報を見て終わるページから、「次の一歩を踏み出しやすいページ」に変わったのです。
結果どうなったか?
- LINEからの予約・相談が増えた
- CTAボタンのクリック率が大幅に改善
- 「LINEって気軽に相談できるんですね」と言われることが増えた
ユーザーは、思っている以上に“なんとなく”でネットを見ています。
だからこそ、「読んだあとに、何をすればいいのか」を具体的に提示すること。
この導線の設計ひとつで、反応はまったく変わってくるのです。
まとめ:ホームページは“伝え方”と“導線設計”で大きく変わる

今回は、伊那市の整体院ホームページの改善事例をもとに、
「見た目は悪くないのに、なぜか反応がない…」という状態から、
“反応が返ってくるサイト”へと変わったプロセスをご紹介しました。
この記事で紹介した改善ポイント
- 誰に向けて書いているのか?を明確にする
→ 「どなたでも歓迎」ではなく、「この人に届けたい」をはっきり言語化 - 情報の順番と見せ方を整える
→ 読者が“自然に読み進めたくなる流れ”を作ることで離脱を防ぐ - 読んだあとに行動しやすくする導線設計
→ LINEや問い合わせへの誘導、行動を促す一言で反応アップ
見た目や機能ももちろん大切ですが、
ホームページで大事なのは「伝わるかどうか」。
たとえば、今のホームページが「作って終わり」になっていたり、
「なんとなく反応がないけど、理由が分からない…」と感じていたら、
ぜひ今回の内容をヒントに“伝え方の改善”を考えてみてください。
モンスターズライティングでは、こんな方をサポートしています
- 自作したホームページに限界を感じている方
- 業者に依頼したけど、いまいち成果につながっていない方
- ちゃんと「伝わるホームページ」に作り直したいと考えている方
最後にひとこと
ホームページは、ちゃんと育てていけば“あなたの代わりに営業してくれる存在”になります。
特別なノウハウがなくても、「誰に・何を・どう伝えるか」を整理するだけで結果は変わります。
小さな改善が、次のお問い合わせや売上アップにつながるかもしれません。
ぜひ、今あるホームページを「もっと働く存在」にしていきましょう。